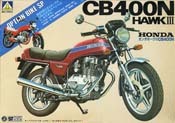前の10件 | -
定年で考えたこと [雑文]
2023年5月末で定年になった。6月からは再雇用して貰って、引き続き同じ会社で働いている。年金が支給されるのは65歳なので、うちの会社では再雇用でプラス5年働く人は多い。よその会社のことは知らないが、たぶん似たようなものなのだろう。
定年になるとお金のことを考える機会が増える。よく聞く話で、「老後資金は、公的年金の他に2000万円必要です」という説。この説の根拠をあまりよく知らなかったので、いつもお世話になっている生命保険のお姉さんに聞いてみた。
この話は令和元年6月の金融庁の報告書(注1)が元になっているらしい。内容としては、夫婦二人の世帯で年金暮らしをしたときに毎月5万円の赤字が生じ、これが30年続くと1800万円になる。だから約2000万円用意しておいた方がよい、というものらしい。
ならば、たとえば赤字が7万円出る人は30年累積すれば2520万円になるわけで、2000万円では足りないということになる。一方65歳から30年たてば95歳だから、そろそろお迎えが来る頃であって「30年」という数字は妥当だと思われる。いずれにせよ自分が年金をいくらもらえるのか、いくらの赤字がでるのか、何歳まで生きるのか、といった数字は個人によってばらつきがでるものなので、そういう見積を一人一人がすべきものなのだ。意味がわかれば漠然とした不安はなくなる。
さて。少し話は変わるが、電車の中だったかネットの広告だったか忘れたが、「DIE WITH ZERO」(注2)という本があることを知った。このタイトルは日本語にすれば「ゼロで死ね」と言う意味なのだが、読んでみて大変考えさせられ刺激を受けた。一言で言うなら「死ぬまでにお金を計画的に使い切って人生を楽しめ」ということだ。
で、そのように言われたときにいろいろな疑問がわくもので、まずは「お金をみんな使ってしまって、そのあとで病気になったらどうするんだ、万一のときのために蓄えておかなきゃ駄目だろう」という疑問、あるいは「お金があれば子供のために残しておいてあげられるではないか」という疑問、などなど。この本は、そうした疑問のひとつひとつに丁寧に答えている。要するに漠然と蓄え、漠然と使い、漠然と残すのではなく、これらすべてに計画性を持てということなのだ。従来型の価値観を書き換えるだけの、きちんとした説得力のある考え方だと思った。
その中でひとつ大いに刺激になったのは、お金を使うタイミングを誤るな、という話。若いときにしか出来ないことというのがある。例えば海外旅行とかスポーツのような体力を使うことは、あまり年をとってしまうと出来なくなってしまう。今60歳で出来ることが、70歳、80歳、90歳になってからはたして出来るのか、という視点が必要になってくる。
寿命が尽きるときに冥土に持って行けるのは、お金ではなく思い出である。そして思い出は経験をしないと得られない。お金を使えば経験できたはずのことが、お金を大切にし過ぎるとできなくなってしまう。死を迎えるときに、いろいろなことを思い出して、楽しい人生だったと思うのか。お金をたくさん持っているのに、あれをすれば良かった、これをすれば良かったと悔やむのか。
「人生で一度は富士山に登りたい」とか「一度でいいから国技館に行って相撲を観戦したい」とか「若い頃からの憧れだったハーレーダビッドソンのバイクに乗りたい」とか。身近な人と話をしていれば、こんな話はいくらも出てくるものだ。振り返って自分のことを考えたとき、僕だって定年になったらあれをやりたいこれもやりたいと、考えていたことはたくさんある。でもそこに優先度をつけなければならないことを自覚していなかった。人に言われてみれば「そりゃそうだ」と思うようなことも、いざ自分がその立場に立ってみないと実感できないことがあるものだ。
さあ、では自分のやりたいことのうちの「どれ」を先ずやるのか。まあ「あのへん」だろうな。なんて定年から8ヶ月を経た今、考えている。・・・と言うか、もう8ヶ月も経ってしまった。ぼやぼやしている場合ではない。時間が経過する速さがどんどん速くなっていく。このスピードは恐ろしいくらいだ。
***
(注1)金融庁 金融審議会 市場ワーキンググループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」 この報告書は公表されているので、検索すれば閲覧できる。
(注2)ビル・パーキンス著 小島修訳 「DIE WITH ZERO」 ダイヤモンド社
定年になるとお金のことを考える機会が増える。よく聞く話で、「老後資金は、公的年金の他に2000万円必要です」という説。この説の根拠をあまりよく知らなかったので、いつもお世話になっている生命保険のお姉さんに聞いてみた。
この話は令和元年6月の金融庁の報告書(注1)が元になっているらしい。内容としては、夫婦二人の世帯で年金暮らしをしたときに毎月5万円の赤字が生じ、これが30年続くと1800万円になる。だから約2000万円用意しておいた方がよい、というものらしい。
ならば、たとえば赤字が7万円出る人は30年累積すれば2520万円になるわけで、2000万円では足りないということになる。一方65歳から30年たてば95歳だから、そろそろお迎えが来る頃であって「30年」という数字は妥当だと思われる。いずれにせよ自分が年金をいくらもらえるのか、いくらの赤字がでるのか、何歳まで生きるのか、といった数字は個人によってばらつきがでるものなので、そういう見積を一人一人がすべきものなのだ。意味がわかれば漠然とした不安はなくなる。
さて。少し話は変わるが、電車の中だったかネットの広告だったか忘れたが、「DIE WITH ZERO」(注2)という本があることを知った。このタイトルは日本語にすれば「ゼロで死ね」と言う意味なのだが、読んでみて大変考えさせられ刺激を受けた。一言で言うなら「死ぬまでにお金を計画的に使い切って人生を楽しめ」ということだ。
で、そのように言われたときにいろいろな疑問がわくもので、まずは「お金をみんな使ってしまって、そのあとで病気になったらどうするんだ、万一のときのために蓄えておかなきゃ駄目だろう」という疑問、あるいは「お金があれば子供のために残しておいてあげられるではないか」という疑問、などなど。この本は、そうした疑問のひとつひとつに丁寧に答えている。要するに漠然と蓄え、漠然と使い、漠然と残すのではなく、これらすべてに計画性を持てということなのだ。従来型の価値観を書き換えるだけの、きちんとした説得力のある考え方だと思った。
その中でひとつ大いに刺激になったのは、お金を使うタイミングを誤るな、という話。若いときにしか出来ないことというのがある。例えば海外旅行とかスポーツのような体力を使うことは、あまり年をとってしまうと出来なくなってしまう。今60歳で出来ることが、70歳、80歳、90歳になってからはたして出来るのか、という視点が必要になってくる。
寿命が尽きるときに冥土に持って行けるのは、お金ではなく思い出である。そして思い出は経験をしないと得られない。お金を使えば経験できたはずのことが、お金を大切にし過ぎるとできなくなってしまう。死を迎えるときに、いろいろなことを思い出して、楽しい人生だったと思うのか。お金をたくさん持っているのに、あれをすれば良かった、これをすれば良かったと悔やむのか。
「人生で一度は富士山に登りたい」とか「一度でいいから国技館に行って相撲を観戦したい」とか「若い頃からの憧れだったハーレーダビッドソンのバイクに乗りたい」とか。身近な人と話をしていれば、こんな話はいくらも出てくるものだ。振り返って自分のことを考えたとき、僕だって定年になったらあれをやりたいこれもやりたいと、考えていたことはたくさんある。でもそこに優先度をつけなければならないことを自覚していなかった。人に言われてみれば「そりゃそうだ」と思うようなことも、いざ自分がその立場に立ってみないと実感できないことがあるものだ。
さあ、では自分のやりたいことのうちの「どれ」を先ずやるのか。まあ「あのへん」だろうな。なんて定年から8ヶ月を経た今、考えている。・・・と言うか、もう8ヶ月も経ってしまった。ぼやぼやしている場合ではない。時間が経過する速さがどんどん速くなっていく。このスピードは恐ろしいくらいだ。
***
(注1)金融庁 金融審議会 市場ワーキンググループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」 この報告書は公表されているので、検索すれば閲覧できる。
(注2)ビル・パーキンス著 小島修訳 「DIE WITH ZERO」 ダイヤモンド社
マンションのリフォームその2 [雑文]
(つづき)
2年くらい前だったか、近くの部屋の人がリフォームでユニットバスを交換したことがあり、その工事を請け負った業者が僕の部屋にも、「交換しませんか」と売り込みに来たことがあった。セールスマンは「マンションも20年過ぎると、配管からの漏水が起りがちになります。そうならない内にいかがでしょうか」と言う。「私は一人暮らしですから一般家庭に比べて使用頻度が低いからそんなに傷まないと思いますよ」と言ったら、「いや、銅管は使用頻度よりも経年で傷むんですよ」と言っていた。
そのときは「そんなものかなあ」と思って、適当にやり過ごしてしまったが、今回、こういうことが起きてみて、あのセールスマンの言っていたことは正しかったんだな、と思った。あの売り込みのあと、僕はぼんやりと「定年になったら退職金を使ってリフォームしようか」と考えていたのだった。僕の定年は2023年5月だ。というわけで、これを4ヶ月前倒しにして、やることにした。
ちなみにこの「ついでに管を交換する」という考えは、管理会社の工事部の人も賛成で「これから先、漏れるか漏れないかは賭けであり、『漏れませんように』と祈りながら生活するより、最新の技術で信頼性の上がった管材に交換した方がよい」との考えだった。
そういうわけで、工事屋さんが、「では最寄りのTOTOのショールームにいって仕様を決めてきてください」というので、厚木のショールームに行った。いままでこういうところに行く機会がなく、今回初めて行ったが、実に楽しいところだった。トイレ、洗面台、キッチンなど家庭の水回り機器を、実際に見て選ぶことができる。説明員の対応も大変わかりやすかった。
仕様が決まり、工事は2023年が明けて1月10日~31日の約3週間。この期間は家具をかたづけないといけないので、最寄りの東横インに仮住まいをすることになった。とは言っても、仕事が終わってホテルに直行では何もすることがない。幸いにして書斎だけには入れるようにしておいたので、普通に帰宅し、寝るときだけホテルに行く生活をすることにした。日中は工事屋さんが工事をし、夕方、作業が終わった頃に僕が帰宅するので、工事の進捗がよくわかって面白かったし、床下の配管やら、ユニットバスの裏側の構造など大変勉強になった。
工事は予定通り終わった。漏水のあった、僕の上のフロアの人との示談書の取り交わしも無事に終わった。入居して何が一番嬉しかったって、漏水事故のおかげで、図らずもリフォームが出来てしまい、家がきれいになったこと。それから、管の交換とユニットバスは自分の持ち出しで工事したが、新しい浴室は実に快適で、毎日風呂に入るのが楽しみで仕方がない。僕はもともと、風呂なんか、体が汚れるから仕方なしに入っているだけで、できることなら入らずに済ませたいと思っていた。それがいまでは、入浴剤を入れて温泉気分に浸って入るのが楽しみになっている。
ということで、きれいになった浴室をお見せしたい。(壁や床を見せてもさほど面白い絵にならないので)
まず全景。



それから、この最新素材の床。乾燥が速く、足を踏み入れると冷たくないし、しかも柔らかい。「ほっカラリ床」という物だそうだ。特に、乾燥が速いのは非常によい。風呂を使っていないときに、浴室に入ることってよくあるが、そのときに、いちいち足を濡らすことがない。なお、傷つきやすい弱点があるそうで、風呂椅子など床に置く物は、足の尖ったものを置かないなどの注意が必要になる。それさえ守っていれば、実に快適である。

それから、排水口に独自の工夫がある。ヘアキャッチャーというもので、中央のまるい窪みに抜け毛が入り、これが水流で転がって毛玉ができる。丸くなった毛の固まりは水の流れで洗われているので、汚くならない。垢もほとんど溜まらない。毛玉が大きくなったら、ポイっと捨てればよい。大変良いアイデアだ。発明した人に拍手を送りたい。(注1)

(注1)僕の場合、男性で髪が短いこともあり、あまり毛玉が大きく成長してくれない。でもTOTOのショールームで見せてもらった毛玉のサンプルは、直径3~4センチくらいの球形だった。このサンプルはもしかしたら、長い髪の女性が3人くらいで生活している家庭(母親と娘2人とか)のものではなかろうか、などと余計な想像をしたりする。(笑)
2年くらい前だったか、近くの部屋の人がリフォームでユニットバスを交換したことがあり、その工事を請け負った業者が僕の部屋にも、「交換しませんか」と売り込みに来たことがあった。セールスマンは「マンションも20年過ぎると、配管からの漏水が起りがちになります。そうならない内にいかがでしょうか」と言う。「私は一人暮らしですから一般家庭に比べて使用頻度が低いからそんなに傷まないと思いますよ」と言ったら、「いや、銅管は使用頻度よりも経年で傷むんですよ」と言っていた。
そのときは「そんなものかなあ」と思って、適当にやり過ごしてしまったが、今回、こういうことが起きてみて、あのセールスマンの言っていたことは正しかったんだな、と思った。あの売り込みのあと、僕はぼんやりと「定年になったら退職金を使ってリフォームしようか」と考えていたのだった。僕の定年は2023年5月だ。というわけで、これを4ヶ月前倒しにして、やることにした。
ちなみにこの「ついでに管を交換する」という考えは、管理会社の工事部の人も賛成で「これから先、漏れるか漏れないかは賭けであり、『漏れませんように』と祈りながら生活するより、最新の技術で信頼性の上がった管材に交換した方がよい」との考えだった。
そういうわけで、工事屋さんが、「では最寄りのTOTOのショールームにいって仕様を決めてきてください」というので、厚木のショールームに行った。いままでこういうところに行く機会がなく、今回初めて行ったが、実に楽しいところだった。トイレ、洗面台、キッチンなど家庭の水回り機器を、実際に見て選ぶことができる。説明員の対応も大変わかりやすかった。
仕様が決まり、工事は2023年が明けて1月10日~31日の約3週間。この期間は家具をかたづけないといけないので、最寄りの東横インに仮住まいをすることになった。とは言っても、仕事が終わってホテルに直行では何もすることがない。幸いにして書斎だけには入れるようにしておいたので、普通に帰宅し、寝るときだけホテルに行く生活をすることにした。日中は工事屋さんが工事をし、夕方、作業が終わった頃に僕が帰宅するので、工事の進捗がよくわかって面白かったし、床下の配管やら、ユニットバスの裏側の構造など大変勉強になった。
工事は予定通り終わった。漏水のあった、僕の上のフロアの人との示談書の取り交わしも無事に終わった。入居して何が一番嬉しかったって、漏水事故のおかげで、図らずもリフォームが出来てしまい、家がきれいになったこと。それから、管の交換とユニットバスは自分の持ち出しで工事したが、新しい浴室は実に快適で、毎日風呂に入るのが楽しみで仕方がない。僕はもともと、風呂なんか、体が汚れるから仕方なしに入っているだけで、できることなら入らずに済ませたいと思っていた。それがいまでは、入浴剤を入れて温泉気分に浸って入るのが楽しみになっている。
ということで、きれいになった浴室をお見せしたい。(壁や床を見せてもさほど面白い絵にならないので)
まず全景。



それから、この最新素材の床。乾燥が速く、足を踏み入れると冷たくないし、しかも柔らかい。「ほっカラリ床」という物だそうだ。特に、乾燥が速いのは非常によい。風呂を使っていないときに、浴室に入ることってよくあるが、そのときに、いちいち足を濡らすことがない。なお、傷つきやすい弱点があるそうで、風呂椅子など床に置く物は、足の尖ったものを置かないなどの注意が必要になる。それさえ守っていれば、実に快適である。

それから、排水口に独自の工夫がある。ヘアキャッチャーというもので、中央のまるい窪みに抜け毛が入り、これが水流で転がって毛玉ができる。丸くなった毛の固まりは水の流れで洗われているので、汚くならない。垢もほとんど溜まらない。毛玉が大きくなったら、ポイっと捨てればよい。大変良いアイデアだ。発明した人に拍手を送りたい。(注1)

(注1)僕の場合、男性で髪が短いこともあり、あまり毛玉が大きく成長してくれない。でもTOTOのショールームで見せてもらった毛玉のサンプルは、直径3~4センチくらいの球形だった。このサンプルはもしかしたら、長い髪の女性が3人くらいで生活している家庭(母親と娘2人とか)のものではなかろうか、などと余計な想像をしたりする。(笑)
マンションのリフォーム [雑文]
最近、ブログの更新が滞っているが、どうしても書いておかないといけないことがあって、半年前から気になっていた。というのは、1年前(2022年7月)に起きた漏水事故(注1)の対応のリフォームが、今年2023年1月末に終了したのだった。
そもそも、マンションには、占有部と共有部というのがあって、共有部(ベランダとか廊下など)のトラブル対応は、全体の保険で対応するのが原則である。しかし今回起った事故は占有部(室内)なので、本来ならば個人が入っている損害保険を使って修理対応するというのがふつうだ。
しかし同じくらいの時期に同じような事故が、僕の案件の前に、3件ほど起きていた。つまりこのマンションも建ってからそれなりの年月が経ったということである。しかもそのうちの一件が損害保険に入っていないという、なんとも不用心な人だったらしい。支払いで揉め事が起るというのは不幸なことだし銅管の寿命(注2)は、ここの住人全体が共通して抱えるリスクだということもあり、マンション全体の保険で対応することになった。
管理会社の工事部が、リフォーム業者に見積もりを依頼し、その金額を保険会社に提示したところ、それを少し削られて、そこから交渉が始まって・・・とやっているうちに、結構な時間がかかってしまったようだ。その間、待っている方は、ずいぶんと気を揉んだ。
見積もりが出たのが10月末で、値段は○○○(3ケタ)万円。これを「現金で受け取る」(注3)か、それとも「現金の授受なしで工事をする」か、どちらかを選べということだったので、迷わず工事を選んだ。そしてその打ち合わせを11月中旬にやったとき、ひとつ相談をした。
今回の見積もりは、被害のあったところを修繕する工事(主にフローリングと壁紙の張り替え)のためのものである。それ以外は入っていない。しかし銅管の漏れがあちこちで起きているということは、次は自分のところで漏れが起きるかもしれない。そうなれば下の階の人がまた被害にあうことになる。そこで「今回、床を張り替えるならば、その機会に床下を這っている管をすべて新しくしてもらえないか。追加料金はどのくらいかかるのだろうか」と相談した。
すると、「温水管がつながっているのは、キッチン、洗面台、洗濯スペース、浴室の4つである。このうち最初の3つは、床を剥がすだけで工事できるが、浴室はユニットバスの壁を剥がさないとできない。壁を剥がすとはつまり壊すことである。結局、管の総交換をするなら、ユニットバスの交換までやらないと意味が無い」との見解をもらった。そのためにだいたいいくらくらいかかるのかも教えてもらった。・・・ということでしばらく考え込んでしまった。(つづく)
*****
(注1)リフレッシュ休暇(3)水漏れ事故
https://shonankit.blog.ss-blog.jp/2022-07-20
4階の部屋から漏れて、3階の僕の部屋を通って、下の階まで浸水した。
(注2)水の管は鉄管、お湯の管は銅管、というのが、このマンションが新築された1999年当時のごく一般的な工法だったらしい。しかし、この銅管が経年で破れてしまう事故が、世の中全体で多く、その後改良され、今ではより寿命の長い樹脂製の管が主流になっているという。
(注3)管理会社の工事部に依頼せず、それ以外の好きな工事業者に頼みたい場合に「現金で受け取る」を選択するようだ。
そもそも、マンションには、占有部と共有部というのがあって、共有部(ベランダとか廊下など)のトラブル対応は、全体の保険で対応するのが原則である。しかし今回起った事故は占有部(室内)なので、本来ならば個人が入っている損害保険を使って修理対応するというのがふつうだ。
しかし同じくらいの時期に同じような事故が、僕の案件の前に、3件ほど起きていた。つまりこのマンションも建ってからそれなりの年月が経ったということである。しかもそのうちの一件が損害保険に入っていないという、なんとも不用心な人だったらしい。支払いで揉め事が起るというのは不幸なことだし銅管の寿命(注2)は、ここの住人全体が共通して抱えるリスクだということもあり、マンション全体の保険で対応することになった。
管理会社の工事部が、リフォーム業者に見積もりを依頼し、その金額を保険会社に提示したところ、それを少し削られて、そこから交渉が始まって・・・とやっているうちに、結構な時間がかかってしまったようだ。その間、待っている方は、ずいぶんと気を揉んだ。
見積もりが出たのが10月末で、値段は○○○(3ケタ)万円。これを「現金で受け取る」(注3)か、それとも「現金の授受なしで工事をする」か、どちらかを選べということだったので、迷わず工事を選んだ。そしてその打ち合わせを11月中旬にやったとき、ひとつ相談をした。
今回の見積もりは、被害のあったところを修繕する工事(主にフローリングと壁紙の張り替え)のためのものである。それ以外は入っていない。しかし銅管の漏れがあちこちで起きているということは、次は自分のところで漏れが起きるかもしれない。そうなれば下の階の人がまた被害にあうことになる。そこで「今回、床を張り替えるならば、その機会に床下を這っている管をすべて新しくしてもらえないか。追加料金はどのくらいかかるのだろうか」と相談した。
すると、「温水管がつながっているのは、キッチン、洗面台、洗濯スペース、浴室の4つである。このうち最初の3つは、床を剥がすだけで工事できるが、浴室はユニットバスの壁を剥がさないとできない。壁を剥がすとはつまり壊すことである。結局、管の総交換をするなら、ユニットバスの交換までやらないと意味が無い」との見解をもらった。そのためにだいたいいくらくらいかかるのかも教えてもらった。・・・ということでしばらく考え込んでしまった。(つづく)
*****
(注1)リフレッシュ休暇(3)水漏れ事故
https://shonankit.blog.ss-blog.jp/2022-07-20
4階の部屋から漏れて、3階の僕の部屋を通って、下の階まで浸水した。
(注2)水の管は鉄管、お湯の管は銅管、というのが、このマンションが新築された1999年当時のごく一般的な工法だったらしい。しかし、この銅管が経年で破れてしまう事故が、世の中全体で多く、その後改良され、今ではより寿命の長い樹脂製の管が主流になっているという。
(注3)管理会社の工事部に依頼せず、それ以外の好きな工事業者に頼みたい場合に「現金で受け取る」を選択するようだ。
姪の結婚式その2(余談) [雑文]
(つづき)
姪は、披露宴の席札を透明レジンの埋め込みで作ってくれた。招待客ひとりひとりの個性に合わせて、中にあしらう物を変えてある。これを35人分、すべて違うデザインで作ったというから大した物だ。心のこもったもてなしに感謝したい。
下は姉のもの。メインの皿の上のナプキンの上に置いてあった。

そしてこちらは僕のもの。機械設計のエンジニアということで歯車がちりばめられている。確かに機械をシンボリックにとらえようとすれば、思い浮かぶのはガチャガチャ動く歯車機構だ。

***
結婚式とか披露宴は、10年位前に会社の後輩に呼ばれて出たのが最後で、それ以来無かった。今回久々に出て、ひとつ気づいたというか、うすうす気づいていたが改めて認識したことがある。それは招待客たちが使っているカメラのことで、余談としてこのことをちょっと書いておきたい。(姪の結婚の話から、だいぶ離れるが、関連記事として)
下の写真はウエディングケーキのカットのシーンだが、周りの人が使っているカメラが写っている。一番右の人はプロのカメラマンで、デジタル一眼レフ。一番左にいる女性も形からデジタル一眼レフとわかる。中央寄りの女性ふたりはスマホを使っている。スマホを使うのが現在の一番一般的なやり方のようだ。

かく言う僕は、コンパクトデジカメ(注1)。現代の流行に照らして見ると、これが一番マイナーだと思われる。(笑)よい写真をきちんと撮ろうと思ったら、一眼レフのようなよいレンズのものを使う。そうでなければ、以前はコンパクトカメラだったのだが、これが今、スマホになっている。もう、コンパクトカメラを使う人はほとんど見かけない。

中学生の頃に天文少年だった僕は、天体写真の撮影に憧れて、それ用の一眼レフカメラに興味をもった。でも中学生の小遣いで買えるようなものではなく、実際に入手することができたのは、大学を卒業して就職した年の1987年だった。これを使って、ずいぶんいろいろな写真を撮った。
言うまでもないかも知れないが、この当時のカメラはフィルム式だった。かつての写真産業というのは、カメラを作るメーカーがあり、フィルムを作るメーカーがあり、そういう機材を販売するカメラ屋があり、撮影したフィルムを現像したり、プリントしたり、さらに焼き増ししたりする店があり・・・というふうに業界が分業して1セットでビジネスになっていた。(注2)
しかし1995年カシオがデジタルカメラを売り出した頃から潮目が変わった。最初の頃は解像度が悪くて話にならないと思っていたが、これがどんどん良くなり、しまいには携帯電話が写真撮影の機能を持つようになった。これがスマホに受け継がれて、現在のこの状況である。上に書いたビジネスの構造が根本的に変わってしまった。というよりほとんど消滅してしまったと言った方が正確だ。
こういうのは時代の流れだと言えばそれまでなのだが、ちょっと切なさを感じる。昔、カメラは時計と並んで精密機械の代表格だった。(注3)ことにカメラには「いじる楽しさ」があった。でも今はそれがない。精密機械ではなく電子機器になってしまった。
自分が機械のエンジニアになったのは、簡単にいうとメカニズムが大好きだったからだが、機械というものは、進化すればするほどガチャガチャ動くところがなくなり、機械らしさがなくなるという変な矛盾を抱えている。しかし、それが進化の方向なら嘆いてもしょうがない。これから先もせいぜい、懐古趣味に浸るのを楽しみにしよう。
*****
(注1)コンパクトデジカメの他にデジタルの一眼レフも持っているが、少なくとも僕の撮影では、スナップ写真レベルだとコンパクトと一眼レフの差が顕著に現れないことに気づいて、それ以来コンパクトだけ使っている。レンズには周辺のゆがみがほとんど無く、光学ズームで20倍使える。しかも掌サイズ。だったらコンパクトの方がいい。ただしプラモを作ってこのブログに載せていた頃は、一眼レフを使っていた。マクロレンズを使えて、小さな部品の撮影で圧倒的に有利なので。
(注2)ヨドバシカメラとかビックカメラとかは、今では、すっかり家電量販店になっているが発祥はその名の通りカメラ屋だった。YouTubeで懐かしいCMを見つけたのでひとつ紹介する。1985年のヨドバシのCMで、一眼レフとコンパクトカメラをずらっと並べてアピールしている。
https://www.youtube.com/watch?v=Xmwh7UBZt_w
一眼レフは、最近はプロか、そうでなければ写真に特別な思い入れのあるごく一部のアマチュアの物になった。コニカとミノルタは合併して、今は写真産業からは撤退した。僕の好きだったペンタックスはリコーに吸収されてしまった。昔から残っているカメラメーカーも、もう写真を主力にしていない。
フィルムも同様で、かつて日本市場にあった富士、コニカ、コダックのうち、残っているのは富士だけだ。(よく生き残ったと思う)コダック(アメリカ)は一回倒産してそのあと再生して別の業種になったらしい。
(注3)カメラが精密機械であった所以はシャッターと、フィルムの巻き上げ機構で、これが連動していた。つまり二重露出を防ぐため、フィルムを送らなければ次のシャッターが切れないようになっていたし、シャッターを押さなければ巻き上げができないようになっていた。1回フィルムを装填してシャッターを切る回数は、36枚撮りフィルムでも、せいぜい40回。でもカメラの愛好家というのは、フィルムを入れずに空シャッターを切り、巻いてまた空シャッターを切る、という「いじる」習性がある。こういうのを入れたら、この機構の動作回数は膨大なものになる。それに耐えられるような設計をしなければならないわけで、そこには設計ノウハウがぎっしり詰まっていたに違いない。でも電子機器になったらこれが全く不要になってしまう。昔、必死で開発したカメラメーカーのエンジニアたちの気持ちを考えると切なくなる。
姪は、披露宴の席札を透明レジンの埋め込みで作ってくれた。招待客ひとりひとりの個性に合わせて、中にあしらう物を変えてある。これを35人分、すべて違うデザインで作ったというから大した物だ。心のこもったもてなしに感謝したい。
下は姉のもの。メインの皿の上のナプキンの上に置いてあった。

そしてこちらは僕のもの。機械設計のエンジニアということで歯車がちりばめられている。確かに機械をシンボリックにとらえようとすれば、思い浮かぶのはガチャガチャ動く歯車機構だ。

***
結婚式とか披露宴は、10年位前に会社の後輩に呼ばれて出たのが最後で、それ以来無かった。今回久々に出て、ひとつ気づいたというか、うすうす気づいていたが改めて認識したことがある。それは招待客たちが使っているカメラのことで、余談としてこのことをちょっと書いておきたい。(姪の結婚の話から、だいぶ離れるが、関連記事として)
下の写真はウエディングケーキのカットのシーンだが、周りの人が使っているカメラが写っている。一番右の人はプロのカメラマンで、デジタル一眼レフ。一番左にいる女性も形からデジタル一眼レフとわかる。中央寄りの女性ふたりはスマホを使っている。スマホを使うのが現在の一番一般的なやり方のようだ。

かく言う僕は、コンパクトデジカメ(注1)。現代の流行に照らして見ると、これが一番マイナーだと思われる。(笑)よい写真をきちんと撮ろうと思ったら、一眼レフのようなよいレンズのものを使う。そうでなければ、以前はコンパクトカメラだったのだが、これが今、スマホになっている。もう、コンパクトカメラを使う人はほとんど見かけない。

中学生の頃に天文少年だった僕は、天体写真の撮影に憧れて、それ用の一眼レフカメラに興味をもった。でも中学生の小遣いで買えるようなものではなく、実際に入手することができたのは、大学を卒業して就職した年の1987年だった。これを使って、ずいぶんいろいろな写真を撮った。
言うまでもないかも知れないが、この当時のカメラはフィルム式だった。かつての写真産業というのは、カメラを作るメーカーがあり、フィルムを作るメーカーがあり、そういう機材を販売するカメラ屋があり、撮影したフィルムを現像したり、プリントしたり、さらに焼き増ししたりする店があり・・・というふうに業界が分業して1セットでビジネスになっていた。(注2)
しかし1995年カシオがデジタルカメラを売り出した頃から潮目が変わった。最初の頃は解像度が悪くて話にならないと思っていたが、これがどんどん良くなり、しまいには携帯電話が写真撮影の機能を持つようになった。これがスマホに受け継がれて、現在のこの状況である。上に書いたビジネスの構造が根本的に変わってしまった。というよりほとんど消滅してしまったと言った方が正確だ。
こういうのは時代の流れだと言えばそれまでなのだが、ちょっと切なさを感じる。昔、カメラは時計と並んで精密機械の代表格だった。(注3)ことにカメラには「いじる楽しさ」があった。でも今はそれがない。精密機械ではなく電子機器になってしまった。
自分が機械のエンジニアになったのは、簡単にいうとメカニズムが大好きだったからだが、機械というものは、進化すればするほどガチャガチャ動くところがなくなり、機械らしさがなくなるという変な矛盾を抱えている。しかし、それが進化の方向なら嘆いてもしょうがない。これから先もせいぜい、懐古趣味に浸るのを楽しみにしよう。
*****
(注1)コンパクトデジカメの他にデジタルの一眼レフも持っているが、少なくとも僕の撮影では、スナップ写真レベルだとコンパクトと一眼レフの差が顕著に現れないことに気づいて、それ以来コンパクトだけ使っている。レンズには周辺のゆがみがほとんど無く、光学ズームで20倍使える。しかも掌サイズ。だったらコンパクトの方がいい。ただしプラモを作ってこのブログに載せていた頃は、一眼レフを使っていた。マクロレンズを使えて、小さな部品の撮影で圧倒的に有利なので。
(注2)ヨドバシカメラとかビックカメラとかは、今では、すっかり家電量販店になっているが発祥はその名の通りカメラ屋だった。YouTubeで懐かしいCMを見つけたのでひとつ紹介する。1985年のヨドバシのCMで、一眼レフとコンパクトカメラをずらっと並べてアピールしている。
https://www.youtube.com/watch?v=Xmwh7UBZt_w
一眼レフは、最近はプロか、そうでなければ写真に特別な思い入れのあるごく一部のアマチュアの物になった。コニカとミノルタは合併して、今は写真産業からは撤退した。僕の好きだったペンタックスはリコーに吸収されてしまった。昔から残っているカメラメーカーも、もう写真を主力にしていない。
フィルムも同様で、かつて日本市場にあった富士、コニカ、コダックのうち、残っているのは富士だけだ。(よく生き残ったと思う)コダック(アメリカ)は一回倒産してそのあと再生して別の業種になったらしい。
(注3)カメラが精密機械であった所以はシャッターと、フィルムの巻き上げ機構で、これが連動していた。つまり二重露出を防ぐため、フィルムを送らなければ次のシャッターが切れないようになっていたし、シャッターを押さなければ巻き上げができないようになっていた。1回フィルムを装填してシャッターを切る回数は、36枚撮りフィルムでも、せいぜい40回。でもカメラの愛好家というのは、フィルムを入れずに空シャッターを切り、巻いてまた空シャッターを切る、という「いじる」習性がある。こういうのを入れたら、この機構の動作回数は膨大なものになる。それに耐えられるような設計をしなければならないわけで、そこには設計ノウハウがぎっしり詰まっていたに違いない。でも電子機器になったらこれが全く不要になってしまう。昔、必死で開発したカメラメーカーのエンジニアたちの気持ちを考えると切なくなる。
姪の結婚式その1 [雑文]
10月22日に、姪の結婚式と披露宴があった。こぢんまりとした式場で、参列者もごく親しい人だけに絞った小さなものだったが、爽やかで非常に雰囲気がよく、楽しい時間を過ごすことができた。新郎も大変人柄の良い人で、こういう人と一緒になれば末永く幸せになれるだろうと安心した。姪が僕の撮影した写真を「ぜひブログに載せてくれ」という。「モザイクなしでそのまま載せてもいいか」と念のためにきいたら「いいよ」というので、そのまま載せる。

姪というのは、姉の子である。姉には子供が二人いて、上が男の子、下が女の子。僕が就職して千葉の実家から神奈川に引っ越したのが1987年だった。甥と姪が生まれたのは、その後だったから、会うのはGWと盆と正月だけだった。それでも、それなりに思い出っていうのはあるものだ。今回は姪が主役なので、姪の思い出をちょっとだけ書いてみようと思う。とは言え、なんだか親馬鹿みたいになってしまいそうなので一つだけ。

姪が小学校の低学年の頃だったと思う。一緒に風呂に入ったときに、ためしに、自分の左右の手の親指の先、中指の先をそれぞれ当てて輪を作り、姪の腹周りを囲んでみた。そしたら、その輪の中に胴がすっぽり入ってしまった。子供の体ってこんなに細いのかとびっくりした。

冷静に考えてみれば、子供は生まれたばかりのサイズからスタートして少しずつ大きくなるわけだから、指で作った輪のサイズよりも胴の方が細い時代があるのは、別段不思議なことではない。でも、僕の場合、自分の子供がいないので、子供の体のサイズというものを実感する機会がなかった。だから、結構印象的な出来事だったのである。
さて。その後、姪は順調に(=健康的に)成長し、一時はだいぶ太った時期もあったようだが、今回ウエディングドレスを着るに当たってジムに通い、1年半かけてなんと約15kgの減量に成功したという。凄い成果だ。かくいう僕も、実は式の3週間前、数年前に作った礼服を着てみたところ、胴回りがパンパンで、ギリギリだったので、3週間かけてダイエットをし、胴回りで数センチ(ベルトの目にして3つ分)の縮小に成功、披露宴のご馳走を余裕で食べられるところまで痩せた(注1)。こういう行事は適度な緊張感が生まれて、いいものだ。
(つづく)
***
(注1)3週間でやったこと。食生活を魚中心にした。それから外食や赤ちょうちんをやめて完全に自炊にして量をコントロール。それからこんにゃくとダイコンだけのおでんを作り置きしておいて、腹が減ったときは、これを食べてしのいだ。体重は3kgくらいしか減らなかったが、腹周りの脂肪がクタクタに柔らかくなり、ベルトを締め付けやすくなった。ベルトの目が詰まったのは、これのせいだと思われる。脂肪が柔らかくなるのは痩せ始めの兆候なのだそうだ。

姪というのは、姉の子である。姉には子供が二人いて、上が男の子、下が女の子。僕が就職して千葉の実家から神奈川に引っ越したのが1987年だった。甥と姪が生まれたのは、その後だったから、会うのはGWと盆と正月だけだった。それでも、それなりに思い出っていうのはあるものだ。今回は姪が主役なので、姪の思い出をちょっとだけ書いてみようと思う。とは言え、なんだか親馬鹿みたいになってしまいそうなので一つだけ。

姪が小学校の低学年の頃だったと思う。一緒に風呂に入ったときに、ためしに、自分の左右の手の親指の先、中指の先をそれぞれ当てて輪を作り、姪の腹周りを囲んでみた。そしたら、その輪の中に胴がすっぽり入ってしまった。子供の体ってこんなに細いのかとびっくりした。

冷静に考えてみれば、子供は生まれたばかりのサイズからスタートして少しずつ大きくなるわけだから、指で作った輪のサイズよりも胴の方が細い時代があるのは、別段不思議なことではない。でも、僕の場合、自分の子供がいないので、子供の体のサイズというものを実感する機会がなかった。だから、結構印象的な出来事だったのである。
さて。その後、姪は順調に(=健康的に)成長し、一時はだいぶ太った時期もあったようだが、今回ウエディングドレスを着るに当たってジムに通い、1年半かけてなんと約15kgの減量に成功したという。凄い成果だ。かくいう僕も、実は式の3週間前、数年前に作った礼服を着てみたところ、胴回りがパンパンで、ギリギリだったので、3週間かけてダイエットをし、胴回りで数センチ(ベルトの目にして3つ分)の縮小に成功、披露宴のご馳走を余裕で食べられるところまで痩せた(注1)。こういう行事は適度な緊張感が生まれて、いいものだ。
(つづく)
***
(注1)3週間でやったこと。食生活を魚中心にした。それから外食や赤ちょうちんをやめて完全に自炊にして量をコントロール。それからこんにゃくとダイコンだけのおでんを作り置きしておいて、腹が減ったときは、これを食べてしのいだ。体重は3kgくらいしか減らなかったが、腹周りの脂肪がクタクタに柔らかくなり、ベルトを締め付けやすくなった。ベルトの目が詰まったのは、これのせいだと思われる。脂肪が柔らかくなるのは痩せ始めの兆候なのだそうだ。
リフレッシュ休暇(3)水漏れ事故 [雑文]
(つづき)
さて、7月4日の下関は、関門トンネルの後、壇ノ浦の合戦で幼くして亡くなった安徳天皇が祀られている赤間神宮を参拝し、唐戸市場でアイスクリームを食べて、16:30頃にホテルにチェックインした。



さて、話はちょっと遡る。
朝、北九州の小倉に向かう新幹線のぞみの車内で、マンションの管理会社からスマホに電話があった。広島を過ぎてもうすぐ新山口に着く頃だった。「ひぐらしさんの部屋の下の部屋で、天井から水漏れがあるので、ひぐらしさんの部屋を調べたいのだが、いつ都合がいい?」という。「今旅行中で帰宅が7月7日の夜になる予定だ」と言った。管理会社は取り急ぎ僕の部屋の水栓をとめた。
その後、前の記事の通り、7月4日は観光したが、心配事があると楽しめない。特に気になったのは、自室で水道の蛇口から水が溢れているかも知れないということだった。可能性のあるところは2カ所あって、一つはトイレのウォシュレットを工事した配管。もうひとつは洗濯機の水をつないでいるカップリング。どちらも僕がこの部屋に入居したあとでつないだものである。この結合部が破れる可能性はないとは言えない。
初日の日程を終えてホテルに入ったが、心配事を抱えて7月7日まで旅行するよりも、いっそのこと帰宅して原因を調べた方が良い。それともうひとつ、翌日の予定は四国の金比羅さんだったのだが、台風4号が来ていて、高知で大雨がふり、その影響で7月5日に四国へ行く路線が2カ所くらい止まりそうだった。
ということで旅行は中止。翌日、下関を始発で出発、昼頃に帰宅した。のぞみは小倉~新横浜を4時間半で走る。このスピードは、こういうとき非常に助かる。
新幹線の中で、管理会社に電話をして、「急遽帰宅することにしたが、部屋に入るときに何か気をつけることはないか」と聞くと、「今日、工事屋さんが下の部屋の養生に入るので、ついでにそちらに行くように状況を伝えておく」とのことだった。
家について、調べてみたら、自分の部屋の廊下の真ん中あたりの天井から水漏れがあって、それが廊下に染み込んでいた。管理会社にその状況を知らせた。それから下の部屋に挨拶にいったら、やはり同じあたりで水漏れがあって、水受けのバケツが置いてあった。昼過ぎに工事屋さんが来た。管理人が上の部屋に知らせて水栓を止めた。やがて水漏れは止まった。
工事屋さんが上の部屋を調べると、台所あたりの水道の配管(床下)から漏れていたらしい。工事屋さんの処置により水漏れは止まった。やっぱり旅行を切り上げて帰宅して正解だった。対応が遅れるほど、僕の部屋と下の部屋の浸水がひどくなっていたはずである。
そのあと工事屋さんは保険請求のために、部屋の被害状況をいろいろ調べていた。廊下だけでなく、廊下の脇の物置にも、水が染みていた。やはりプロの目は素人とは違ってよく行き届くようだ。それから修理代はマンションが団体で入っている保険から出るようだが、思ったより規模の大きい修理になりそう。
とりあえず、自分の部屋が原因でないことがわかり、ほっとしたが、確率的にみれば、僕の部屋から漏水することだってあるので、安心ばかりしてはいられない。それから、工事屋さんによると、このマンションの漏水事故は今回が初めてなのではなく、すでに2件くらい発生しているそうだ。やはり20年を越えるとこういうことが徐々に起きてくる。こういうのはマンションの弱点だと思う。
なお、台風4号は7月5日の夜頃に温帯低気圧に変わったらしい。
(つづく)
***
さて、7月4日の下関は、関門トンネルの後、壇ノ浦の合戦で幼くして亡くなった安徳天皇が祀られている赤間神宮を参拝し、唐戸市場でアイスクリームを食べて、16:30頃にホテルにチェックインした。
さて、話はちょっと遡る。
朝、北九州の小倉に向かう新幹線のぞみの車内で、マンションの管理会社からスマホに電話があった。広島を過ぎてもうすぐ新山口に着く頃だった。「ひぐらしさんの部屋の下の部屋で、天井から水漏れがあるので、ひぐらしさんの部屋を調べたいのだが、いつ都合がいい?」という。「今旅行中で帰宅が7月7日の夜になる予定だ」と言った。管理会社は取り急ぎ僕の部屋の水栓をとめた。
その後、前の記事の通り、7月4日は観光したが、心配事があると楽しめない。特に気になったのは、自室で水道の蛇口から水が溢れているかも知れないということだった。可能性のあるところは2カ所あって、一つはトイレのウォシュレットを工事した配管。もうひとつは洗濯機の水をつないでいるカップリング。どちらも僕がこの部屋に入居したあとでつないだものである。この結合部が破れる可能性はないとは言えない。
初日の日程を終えてホテルに入ったが、心配事を抱えて7月7日まで旅行するよりも、いっそのこと帰宅して原因を調べた方が良い。それともうひとつ、翌日の予定は四国の金比羅さんだったのだが、台風4号が来ていて、高知で大雨がふり、その影響で7月5日に四国へ行く路線が2カ所くらい止まりそうだった。
ということで旅行は中止。翌日、下関を始発で出発、昼頃に帰宅した。のぞみは小倉~新横浜を4時間半で走る。このスピードは、こういうとき非常に助かる。
新幹線の中で、管理会社に電話をして、「急遽帰宅することにしたが、部屋に入るときに何か気をつけることはないか」と聞くと、「今日、工事屋さんが下の部屋の養生に入るので、ついでにそちらに行くように状況を伝えておく」とのことだった。
家について、調べてみたら、自分の部屋の廊下の真ん中あたりの天井から水漏れがあって、それが廊下に染み込んでいた。管理会社にその状況を知らせた。それから下の部屋に挨拶にいったら、やはり同じあたりで水漏れがあって、水受けのバケツが置いてあった。昼過ぎに工事屋さんが来た。管理人が上の部屋に知らせて水栓を止めた。やがて水漏れは止まった。
工事屋さんが上の部屋を調べると、台所あたりの水道の配管(床下)から漏れていたらしい。工事屋さんの処置により水漏れは止まった。やっぱり旅行を切り上げて帰宅して正解だった。対応が遅れるほど、僕の部屋と下の部屋の浸水がひどくなっていたはずである。
そのあと工事屋さんは保険請求のために、部屋の被害状況をいろいろ調べていた。廊下だけでなく、廊下の脇の物置にも、水が染みていた。やはりプロの目は素人とは違ってよく行き届くようだ。それから修理代はマンションが団体で入っている保険から出るようだが、思ったより規模の大きい修理になりそう。
とりあえず、自分の部屋が原因でないことがわかり、ほっとしたが、確率的にみれば、僕の部屋から漏水することだってあるので、安心ばかりしてはいられない。それから、工事屋さんによると、このマンションの漏水事故は今回が初めてなのではなく、すでに2件くらい発生しているそうだ。やはり20年を越えるとこういうことが徐々に起きてくる。こういうのはマンションの弱点だと思う。
なお、台風4号は7月5日の夜頃に温帯低気圧に変わったらしい。
(つづく)
***
リフレッシュ休暇(2)下関その2 [雑文]
下関側から門司へ伸びる関門橋。みもすそ川のバス停で降りて海に向かうと、橋は右側にある。写真を撮ろうとすると、橋に近すぎて、画角に収まりきれない。間近で見るとすごい迫力である。



関門海峡を渡る交通経路は、グーグルの地図で見ると、4つあることがわかる。


南から北へ向かって、JR在来線、高速道路、一般道路、JR新幹線の4つであるが、このうち、橋が架かっているのは、高速道路(関門橋)だけであって、残り3つは海底トンネルである。それで、この4つの経路のどれがいつ頃出来たのか調べてみたところ・・・
1)関門鉄道トンネル(JR山陽本線)・・・1944年
2)関門国道トンネル(国道2号線)・・・1958年
3)関門橋(高速道路)・・・・・・・・・1973年
4)新関門トンネル(JR山陽新幹線)・・・1975年
・・・ということのようだ。一番古いものが貫通したのが、なんと戦時中。一番新しい新幹線でも1975年。4つとも意外に古い時期に完成していることに驚かされた。(注1)
さて、上記2)の関門国道トンネルは、壇ノ浦の古戦場跡のすぐ近くを通っているが、ここのトンネルには車道に平行して人道(要するに歩道)が作られていて、歩いて渡ることができるようになっている。渡ってみた。(実はこれ、結構楽しみだったんだ)
まずエレベーターで地下に下る。



スタート地点

下関と門司の境目

門司に到着。歩いてわずか10分、僕の歩く速さから換算すると距離は860 m くらいだろうか。


地上にでて、下関側を眺めて考えた。この距離の近さは、海というより、大きめの川である。平家がここで源氏を迎撃したのが、なんとなく理解できる。
源氏側が、彦島に逃げ込んだ平家をどう攻めるか、と考えたときに、取り囲んで兵糧攻めにする方法もあったと思うのだが、義経はそうしなかった。(注2)直接的な攻撃をするなら、この海峡を通って彦島を目指す。平家を陸路で攻めても、どうせ海に逃げてしまうことが屋島の合戦でわかっていた。また平家方にとっては、逆にこの一番幅の狭い壇ノ浦のあたりで、なんとしても食い止めなければならなかったのだろう。
実際にこの地にきて、トンネルを歩いて海峡を渡ってみて、サイズを実感し、戦に関わった人の感覚が少しわかった気がする。(もちろんこれは歴史の専門家ではない素人の感じた事なので、ちゃんと勉強中の方は鵜呑みにしないでいただきたい)
ここにトンネルや橋が作られているのも納得がいく。つまり一番狭いところにトンネルを掘り、橋を架ければ、工事が楽でコストを抑えられるのだ。壇ノ浦の古戦場と、海峡を結ぶトンネルや橋が同じところにあることになんの疑問も抱かなかったが、これは単なる偶然ではなく、地形的な理由があるということである。
下関側のエレベーターのところに紙芝居のお姉さんがいて「耳なし芳一」をやっていた。写真は、芳一の物語が終わって平家の亡霊たちが泣いている場面。

***
(注1)参考情報。他の場所に目を向けると、青函トンネルも瀬戸大橋も同じく1988年に開通だそうだ。このくらいの時代になると「わりと最近だな」という感覚になるが、1970年代となると「結構昔だ」と感じる。まあ、これは感じる人の年齢による話。
(注2)兵糧攻めは、攻められる方が苦しいのはもちろんだが、攻める側にもかなりの負担がかかる。つまり、大勢の侍を長いこと待機させれば、当然食料が必要になるし、長期に及べば、せっかく源氏方についてくれた侍たちの志気の低下も問題になってくる。そう簡単でない。戦の規模がある程度小さくならないと、この戦法は使えないと思われる。
関門海峡を渡る交通経路は、グーグルの地図で見ると、4つあることがわかる。


南から北へ向かって、JR在来線、高速道路、一般道路、JR新幹線の4つであるが、このうち、橋が架かっているのは、高速道路(関門橋)だけであって、残り3つは海底トンネルである。それで、この4つの経路のどれがいつ頃出来たのか調べてみたところ・・・
1)関門鉄道トンネル(JR山陽本線)・・・1944年
2)関門国道トンネル(国道2号線)・・・1958年
3)関門橋(高速道路)・・・・・・・・・1973年
4)新関門トンネル(JR山陽新幹線)・・・1975年
・・・ということのようだ。一番古いものが貫通したのが、なんと戦時中。一番新しい新幹線でも1975年。4つとも意外に古い時期に完成していることに驚かされた。(注1)
さて、上記2)の関門国道トンネルは、壇ノ浦の古戦場跡のすぐ近くを通っているが、ここのトンネルには車道に平行して人道(要するに歩道)が作られていて、歩いて渡ることができるようになっている。渡ってみた。(実はこれ、結構楽しみだったんだ)
まずエレベーターで地下に下る。
スタート地点
下関と門司の境目
門司に到着。歩いてわずか10分、僕の歩く速さから換算すると距離は860 m くらいだろうか。
地上にでて、下関側を眺めて考えた。この距離の近さは、海というより、大きめの川である。平家がここで源氏を迎撃したのが、なんとなく理解できる。
源氏側が、彦島に逃げ込んだ平家をどう攻めるか、と考えたときに、取り囲んで兵糧攻めにする方法もあったと思うのだが、義経はそうしなかった。(注2)直接的な攻撃をするなら、この海峡を通って彦島を目指す。平家を陸路で攻めても、どうせ海に逃げてしまうことが屋島の合戦でわかっていた。また平家方にとっては、逆にこの一番幅の狭い壇ノ浦のあたりで、なんとしても食い止めなければならなかったのだろう。
実際にこの地にきて、トンネルを歩いて海峡を渡ってみて、サイズを実感し、戦に関わった人の感覚が少しわかった気がする。(もちろんこれは歴史の専門家ではない素人の感じた事なので、ちゃんと勉強中の方は鵜呑みにしないでいただきたい)
ここにトンネルや橋が作られているのも納得がいく。つまり一番狭いところにトンネルを掘り、橋を架ければ、工事が楽でコストを抑えられるのだ。壇ノ浦の古戦場と、海峡を結ぶトンネルや橋が同じところにあることになんの疑問も抱かなかったが、これは単なる偶然ではなく、地形的な理由があるということである。
下関側のエレベーターのところに紙芝居のお姉さんがいて「耳なし芳一」をやっていた。写真は、芳一の物語が終わって平家の亡霊たちが泣いている場面。
***
(注1)参考情報。他の場所に目を向けると、青函トンネルも瀬戸大橋も同じく1988年に開通だそうだ。このくらいの時代になると「わりと最近だな」という感覚になるが、1970年代となると「結構昔だ」と感じる。まあ、これは感じる人の年齢による話。
(注2)兵糧攻めは、攻められる方が苦しいのはもちろんだが、攻める側にもかなりの負担がかかる。つまり、大勢の侍を長いこと待機させれば、当然食料が必要になるし、長期に及べば、せっかく源氏方についてくれた侍たちの志気の低下も問題になってくる。そう簡単でない。戦の規模がある程度小さくならないと、この戦法は使えないと思われる。
リフレッシュ休暇(1)下関その1 [雑文]
僕が今の会社に就職したのは1987年だった。2012年に勤続25年になり、リフレッシュ休暇をもらった。2013年に書いた「ひぐらし大旅行」というシリーズものの記事はこのときのものだった。(注1)
今年は2022年、勤続35年でまたリフレッシュ休暇をもらうことになった。(注2)
長い休みをもらったら旅行に行きたい。でも前回と違って、今回は両親の健康が心配で、あまり長い期間の旅行にはちょっと抵抗があった。いろいろ考えた結果、日程は3泊4日の計画にした。初日は下関。壇ノ浦の古戦場を見てみたかったのだ。
7月4日、早朝、新横浜発6:51発ののぞみ5号にのり、11:14に小倉に到着。わずか4時間半、このスピードは驚異的である。そこから山陽本線に乗って下関へ。下関の駅からバスにのって、みもすそ川(注3)というバス停で降りるとその辺一帯が壇ノ浦の古戦場として整備されている。
早速、源義経と平知盛の像に対面した。義経の方は八艘飛び、知盛の方は碇を抱えて入水するところを造形したようだ。二人ともやたら男前である。




ところで、義経の八艘飛びも、知盛の碇も、平家物語の記述とは違いがある。僕は最初、これは写本による違いなのかと思っていたが、実際はそうではなく、後世の歌舞伎や能で、そのような脚色が為されたらしい。まあ、その方がドラマチックで絵になる。
実際に平家物語でどう書かれているか、読み返してみた。まず八艘飛びの元になったと思われる場面。ここは能登守教経(のりつね)が義経を討とうと、義経の舟に飛び乗ったところ、義経が形勢不利とみて、他の舟にひらりと飛び移ったという場面である。教経は追い切れず、源氏方の侍二人を両脇に抱えて道連れにして入水した。(本文中、判官というのが義経のこと)

それから、知盛が入水する場面は、平家物語の本文では、鎧を二枚重ね着して(水に浮かないようにして)沈んだということになっている。(文中、新中納言というのが知盛のこと)

ただし碇を抱えて入水するという脚色のヒントになったらしい場面が他にある。これは教盛(のりもり)と経盛(つねもり)が入水するシーンで、この兄弟が鎧の上に碇を背負い、一緒に海に入ったと書かれている。

最近フジテレビで、アニメの平家物語が放送されたが、最終回では、知盛が碇を抱えるシーンがきちんと描かれていた。(AmazonのPrime Videoで今、無料で見られる)

(つづく)
***
(注1)興味のある方、下記URLを参照
https://shonankit.blog.ss-blog.jp/2013-11-27
(注2)制度としては休みを勤続35年でもらうか、または停年前1年でもらうかの二者択一になっている。どちらも内容は同じなのだが、学歴によっては勤続35年に満たないまま停年になる人がいるので、それに配慮されているらしい。
(注3) みもすそ川・・・漢字では「御裳川」と書くらしいが、ひらがな表記が公式になっている。ここの町名も「下関市みもすそ川町」という。おそらく他所から観光で訪れる人が読めなくて不便なので、ひらがな表記にしたのだろう。
今年は2022年、勤続35年でまたリフレッシュ休暇をもらうことになった。(注2)
長い休みをもらったら旅行に行きたい。でも前回と違って、今回は両親の健康が心配で、あまり長い期間の旅行にはちょっと抵抗があった。いろいろ考えた結果、日程は3泊4日の計画にした。初日は下関。壇ノ浦の古戦場を見てみたかったのだ。
7月4日、早朝、新横浜発6:51発ののぞみ5号にのり、11:14に小倉に到着。わずか4時間半、このスピードは驚異的である。そこから山陽本線に乗って下関へ。下関の駅からバスにのって、みもすそ川(注3)というバス停で降りるとその辺一帯が壇ノ浦の古戦場として整備されている。
早速、源義経と平知盛の像に対面した。義経の方は八艘飛び、知盛の方は碇を抱えて入水するところを造形したようだ。二人ともやたら男前である。




ところで、義経の八艘飛びも、知盛の碇も、平家物語の記述とは違いがある。僕は最初、これは写本による違いなのかと思っていたが、実際はそうではなく、後世の歌舞伎や能で、そのような脚色が為されたらしい。まあ、その方がドラマチックで絵になる。
実際に平家物語でどう書かれているか、読み返してみた。まず八艘飛びの元になったと思われる場面。ここは能登守教経(のりつね)が義経を討とうと、義経の舟に飛び乗ったところ、義経が形勢不利とみて、他の舟にひらりと飛び移ったという場面である。教経は追い切れず、源氏方の侍二人を両脇に抱えて道連れにして入水した。(本文中、判官というのが義経のこと)
それから、知盛が入水する場面は、平家物語の本文では、鎧を二枚重ね着して(水に浮かないようにして)沈んだということになっている。(文中、新中納言というのが知盛のこと)
ただし碇を抱えて入水するという脚色のヒントになったらしい場面が他にある。これは教盛(のりもり)と経盛(つねもり)が入水するシーンで、この兄弟が鎧の上に碇を背負い、一緒に海に入ったと書かれている。
最近フジテレビで、アニメの平家物語が放送されたが、最終回では、知盛が碇を抱えるシーンがきちんと描かれていた。(AmazonのPrime Videoで今、無料で見られる)
(つづく)
***
(注1)興味のある方、下記URLを参照
https://shonankit.blog.ss-blog.jp/2013-11-27
(注2)制度としては休みを勤続35年でもらうか、または停年前1年でもらうかの二者択一になっている。どちらも内容は同じなのだが、学歴によっては勤続35年に満たないまま停年になる人がいるので、それに配慮されているらしい。
(注3) みもすそ川・・・漢字では「御裳川」と書くらしいが、ひらがな表記が公式になっている。ここの町名も「下関市みもすそ川町」という。おそらく他所から観光で訪れる人が読めなくて不便なので、ひらがな表記にしたのだろう。
平家物語を読みたい(17) 平家滅亡 [読書]
最後に壇ノ浦の合戦のあとを含め、平家一族(注1)がどうなったかまとめてみた。ただ人数が多いので、清盛の子供、孫あたりに絞る。
まず長男の重盛と次男の基盛は父親よりも先に亡くなっている。重盛の長男の維盛は都落ちの最中に屋島を抜け出して滝口入道を訪ね熊野で入水した。(これは「維盛と滝口入道」のところで紹介)その息子の六代(注2)は、壇ノ浦が終わった時点で8歳だった。
嫡系中の嫡系であったが幼かったので、女房たちが文覚(頼朝に蜂起を勧めた僧)に助けを求めた。文覚は鎌倉まで行き頼朝に六代の助命を嘆願し、結果、助けられた。頼朝の立場としては文覚にも義理があったし、また平治の乱のときに、清盛に殺されるところを重盛に助けられた恩があったので、その孫を助けた形になった(注3)。
その後、六代は出家して仏道修行に励んでいたが、20年ほどたって(時は鎌倉時代)文覚が不祥事を起こしたときに連座責任で30歳を過ぎたころに殺された。この人が死んだ時点で、清盛の子孫の男系が完全に滅びたことになる。
三男の宗盛。二人の兄が早く亡くなってしまったので、嫡男として一族を率いる立場になったが、この人は元々そういう方面に向いていない人で、平家物語では、かなりカッコ悪い役回りになっている。そもそも義仲が京に攻め寄せたときに、戦いもせずに都落ちを決めたというのが、すでにカッコ悪い。
さらに壇ノ浦では、みんなが入水するから自分も入水しようか、と迷っていたので、見ていた近くの侍がイライラして海にドボンと突き落とした。これを見た息子の清宗も一緒に飛び込んだ。ところが親子そろって泳ぎが得意だったため死にきれず、清宗は「父上が沈んだらあとを追う」と思い、宗盛は「息子が沈んだらあとを追う」と思い、互いに様子を見て浮いていたら、源氏に助けられてしまった。
義経は宗盛親子を捕虜として鎌倉に連行した。その道中で宗盛は義経に「なんとか助けてくれ」と命乞いをしている。義経は「鎌倉殿は情け深い方だから島流しくらいで助かるだろう」などと慰めたが「たとえ流されるのが蝦夷地であっても生きていたいものだ」などと言ったという。武士としては、かなり情けない部類の人ではないだろうか。まあ情けないとは言っても一応、平家の総大将である。結局、宗盛親子は、頼朝に面会したあと、京に戻される途中の近江の国(滋賀県)の篠原というところで斬首された。
四男の知盛は、壇ノ浦で最後まで戦って入水。五男の重衡は一の谷で捕虜になり頼朝の指図で伊豆に軟禁されていたが、壇ノ浦のあと奈良焼き討ちの責めを負い、奈良に連行されて斬首された。(このシリーズの「重衡と千手前」で紹介)
最後に建礼門院徳子。壇ノ浦では安徳天皇(=自分の子供)と一緒に入水したが、源氏方に助けられ捕虜になった。その後、他の生き残った女房たちとともに出家して、大原の寂光院という庵に住んで、一族の菩提を弔いつつ天寿を全うしたという。平家物語は全12巻であるが、そのあとに1巻だけ番外編のような位置づけで、灌頂巻(かんぢょうのまき)(注4)というのがあって、ここにそのいきさつが書かれている。
壇ノ浦が終わって1年ほど経ったある日、後白河院が寂光院を前触れもなく訪ねた。このときに建礼門院が自分の人生を六道輪廻(注5)になぞらえて語るシーンが興味深い。清盛の娘として高倉天皇に嫁ぎ、皆にかしずかれて暮らしていた頃は極楽のようだった。義仲に攻められて都落ちをしたときは人間界の怨憎会苦、愛別離苦を経験した。大宰府を追われ海上を彷徨い、真水が飲めなくて苦しんだときは餓鬼道とはこういうものかと思ったし、その後の瀬戸内の戦は修羅の世界、壇ノ浦でみなが次々に斬られ入水するところは地獄とはこういうところかと思ったという。
平家物語の最後は、この寂光庵の尼僧たちがみな往生を遂げたところで終わっている。荒々しい戦や戦後処理が終わり、ラストは穏やかな、涅槃寂静を思わせるシーンで終わる。ハッピーエンドではないけれども、この終わり方は上手で、爽やかだなと思った。
***
長いこと書いてきた「平家物語を読みたい」のシリーズはこれにて終了する。小学館の「日本古典文学全集」のシリーズは、大変勉強しやすい本だった。この本のおかげで古典を読む楽しさを十分に味わうことができたと思っている。勉強会に誘ってくれた姉にも感謝。(記事を読んでくださった皆さんも、ありがとうございました)
・・・ついでに。2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が始まっている。今日の時点で2回が放送され大変面白い。伊豆に流されていた源頼朝が蜂起し、平家を滅ぼして鎌倉幕府を開き、そのあと北条氏が受け継いで・・・という話になっていくらしい。平家方から見ると壇ノ浦=滅亡であるが、源氏方からみると、まだ夢の途中である。
源平の争乱と明治維新は以前から大河ドラマでは何度も取り上げられている。やっぱり大革命というのはドラマの宝庫なのだろう。(おわり)
***
(注1)「平氏」という言葉は、桓武天皇から臣籍降下して「平(たいら)」という姓を名乗る一群の人々を指すが、「平家」といった場合は慣例的に平清盛の一族を指すのだそうだ。これは今回初めて知った。
(注2)平正盛(清盛の祖父)から数えて六代目だから六代というのだそうだが、なぜそこから数えるのか不明。いずれにしても名前はあるらしいが、平家物語では一貫して六代と呼ばれているので、ここでもそう呼ぶ。
(注3)平治の乱のときに頼朝は13歳くらいだった。本来ならば清盛に殺されるところを、池禅尼(清盛の継母)が助命を嘆願、清盛の弟の頼盛と長男の重盛が代わる代わる清盛の説得に当たり、結果、助命されて伊豆に流されたという経緯があり、頼朝は、頼盛と重盛には恩義を感じていた。
(注4)灌頂(かんぢょう)・・・仏教の言葉で、頭に水を灌ぐ儀式を表す言葉で、仏道修行の最後の仕上げにこれをやるらしいが、平家物語では、建礼門院の晩年を修行の最終段階に見立ててこのようなタイトルになっているらしい。
(注5)六道輪廻・・・仏教の人生観。極楽、地獄、人間、修羅、餓鬼、畜生の六つの世界があって、人間は死んでも転生(生まれ変わり)して、この六つの世界をめぐるという思想。例えば、人間界で無駄に動物を殺した人にはバチが当たって、来世は畜生道(動物の世界)に落ちる、などという考え方。
まず長男の重盛と次男の基盛は父親よりも先に亡くなっている。重盛の長男の維盛は都落ちの最中に屋島を抜け出して滝口入道を訪ね熊野で入水した。(これは「維盛と滝口入道」のところで紹介)その息子の六代(注2)は、壇ノ浦が終わった時点で8歳だった。
嫡系中の嫡系であったが幼かったので、女房たちが文覚(頼朝に蜂起を勧めた僧)に助けを求めた。文覚は鎌倉まで行き頼朝に六代の助命を嘆願し、結果、助けられた。頼朝の立場としては文覚にも義理があったし、また平治の乱のときに、清盛に殺されるところを重盛に助けられた恩があったので、その孫を助けた形になった(注3)。
その後、六代は出家して仏道修行に励んでいたが、20年ほどたって(時は鎌倉時代)文覚が不祥事を起こしたときに連座責任で30歳を過ぎたころに殺された。この人が死んだ時点で、清盛の子孫の男系が完全に滅びたことになる。
三男の宗盛。二人の兄が早く亡くなってしまったので、嫡男として一族を率いる立場になったが、この人は元々そういう方面に向いていない人で、平家物語では、かなりカッコ悪い役回りになっている。そもそも義仲が京に攻め寄せたときに、戦いもせずに都落ちを決めたというのが、すでにカッコ悪い。
さらに壇ノ浦では、みんなが入水するから自分も入水しようか、と迷っていたので、見ていた近くの侍がイライラして海にドボンと突き落とした。これを見た息子の清宗も一緒に飛び込んだ。ところが親子そろって泳ぎが得意だったため死にきれず、清宗は「父上が沈んだらあとを追う」と思い、宗盛は「息子が沈んだらあとを追う」と思い、互いに様子を見て浮いていたら、源氏に助けられてしまった。
義経は宗盛親子を捕虜として鎌倉に連行した。その道中で宗盛は義経に「なんとか助けてくれ」と命乞いをしている。義経は「鎌倉殿は情け深い方だから島流しくらいで助かるだろう」などと慰めたが「たとえ流されるのが蝦夷地であっても生きていたいものだ」などと言ったという。武士としては、かなり情けない部類の人ではないだろうか。まあ情けないとは言っても一応、平家の総大将である。結局、宗盛親子は、頼朝に面会したあと、京に戻される途中の近江の国(滋賀県)の篠原というところで斬首された。
四男の知盛は、壇ノ浦で最後まで戦って入水。五男の重衡は一の谷で捕虜になり頼朝の指図で伊豆に軟禁されていたが、壇ノ浦のあと奈良焼き討ちの責めを負い、奈良に連行されて斬首された。(このシリーズの「重衡と千手前」で紹介)
最後に建礼門院徳子。壇ノ浦では安徳天皇(=自分の子供)と一緒に入水したが、源氏方に助けられ捕虜になった。その後、他の生き残った女房たちとともに出家して、大原の寂光院という庵に住んで、一族の菩提を弔いつつ天寿を全うしたという。平家物語は全12巻であるが、そのあとに1巻だけ番外編のような位置づけで、灌頂巻(かんぢょうのまき)(注4)というのがあって、ここにそのいきさつが書かれている。
壇ノ浦が終わって1年ほど経ったある日、後白河院が寂光院を前触れもなく訪ねた。このときに建礼門院が自分の人生を六道輪廻(注5)になぞらえて語るシーンが興味深い。清盛の娘として高倉天皇に嫁ぎ、皆にかしずかれて暮らしていた頃は極楽のようだった。義仲に攻められて都落ちをしたときは人間界の怨憎会苦、愛別離苦を経験した。大宰府を追われ海上を彷徨い、真水が飲めなくて苦しんだときは餓鬼道とはこういうものかと思ったし、その後の瀬戸内の戦は修羅の世界、壇ノ浦でみなが次々に斬られ入水するところは地獄とはこういうところかと思ったという。
平家物語の最後は、この寂光庵の尼僧たちがみな往生を遂げたところで終わっている。荒々しい戦や戦後処理が終わり、ラストは穏やかな、涅槃寂静を思わせるシーンで終わる。ハッピーエンドではないけれども、この終わり方は上手で、爽やかだなと思った。
***
長いこと書いてきた「平家物語を読みたい」のシリーズはこれにて終了する。小学館の「日本古典文学全集」のシリーズは、大変勉強しやすい本だった。この本のおかげで古典を読む楽しさを十分に味わうことができたと思っている。勉強会に誘ってくれた姉にも感謝。(記事を読んでくださった皆さんも、ありがとうございました)
・・・ついでに。2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が始まっている。今日の時点で2回が放送され大変面白い。伊豆に流されていた源頼朝が蜂起し、平家を滅ぼして鎌倉幕府を開き、そのあと北条氏が受け継いで・・・という話になっていくらしい。平家方から見ると壇ノ浦=滅亡であるが、源氏方からみると、まだ夢の途中である。
源平の争乱と明治維新は以前から大河ドラマでは何度も取り上げられている。やっぱり大革命というのはドラマの宝庫なのだろう。(おわり)
***
(注1)「平氏」という言葉は、桓武天皇から臣籍降下して「平(たいら)」という姓を名乗る一群の人々を指すが、「平家」といった場合は慣例的に平清盛の一族を指すのだそうだ。これは今回初めて知った。
(注2)平正盛(清盛の祖父)から数えて六代目だから六代というのだそうだが、なぜそこから数えるのか不明。いずれにしても名前はあるらしいが、平家物語では一貫して六代と呼ばれているので、ここでもそう呼ぶ。
(注3)平治の乱のときに頼朝は13歳くらいだった。本来ならば清盛に殺されるところを、池禅尼(清盛の継母)が助命を嘆願、清盛の弟の頼盛と長男の重盛が代わる代わる清盛の説得に当たり、結果、助命されて伊豆に流されたという経緯があり、頼朝は、頼盛と重盛には恩義を感じていた。
(注4)灌頂(かんぢょう)・・・仏教の言葉で、頭に水を灌ぐ儀式を表す言葉で、仏道修行の最後の仕上げにこれをやるらしいが、平家物語では、建礼門院の晩年を修行の最終段階に見立ててこのようなタイトルになっているらしい。
(注5)六道輪廻・・・仏教の人生観。極楽、地獄、人間、修羅、餓鬼、畜生の六つの世界があって、人間は死んでも転生(生まれ変わり)して、この六つの世界をめぐるという思想。例えば、人間界で無駄に動物を殺した人にはバチが当たって、来世は畜生道(動物の世界)に落ちる、などという考え方。
平家物語を読みたい(16) 決戦!壇ノ浦 [読書]
さて、屋島の合戦が終わったあと、平家一族は、彦島に逃げ込んだ。ここは、本州の最西端である。

壇ノ浦の合戦の前、平家を取り巻く環境がどうなっていたのかをちょっと整理してみた。というのは、屋島が終わったあと、近くの有力者たちの寝返りが結構起きていて、壇ノ浦のとき、実際はもう放っておいても負けるような状態になっていたのだ。
まず九州。義仲に京を攻められて都落ちをしたときに、平家一族は一旦太宰府に入ろうとしたが、地元の侍がすべて源氏方についていて追い出されてしまい、居場所がなくなった結果、屋島に落ち着いたという経緯があった。
つぎに熊野権現の別当、湛増(注1)。この人はもともと平清盛と良好な関係にあったが、戦況が源氏に有利になり、リーダーとして源氏につくか、平家につくかの判断を迫られた。平家物語には書かれていないが、源氏と平家、双方から味方につくように迫られていたようで、中立という選択肢はなかったようだ。湛増は戦の行方を闘鶏で占い、源氏につくことにしたという。平家にとっては神に見放されたも同じである。
それから、四国の有力武将たち。伊予の武将、河野通信(こうのみちのぶ)、この人はもともと源氏方だった。彦島に対して四国のこの位置に味方がいるというのは源氏方にとってはかなり有利だったのではないか。
また四国の最大勢力の田口家は平家方であったが、屋島のあと、義経の部下の説得工作により田口教能(たぐちのりよし)が投降。総勢3000騎が源氏方につくことになった。そして極めつけが、田口重能(たぐちしげよし)。この人は田口教能の父親で、壇ノ浦の合戦の直前、息子が源氏方についたことを知り、合戦の最中に寝返り、勝敗を決定つけることになる。
・・・という四面楚歌の状態である。こういう場合、現代人ならば、おそらくほとんどの人が「もう無駄な殺生はやめ、平和的な説得工作に徹した方がいいのではないか」と考えるだろうし、実際そういう考えもあったらしい(注2)が、当時の武士の使命感が「敵と戦って首を取り、勝って報償をもらうこと」なので、何もせずに静観するということは、結局できなかったのではないか。これは僕の想像である。
さて源氏が瀬戸内海側、つまり東側から彦島に攻め込もうとすれば、関門海峡を通る必要がある。屋島が終わって1ヶ月後の3月。壇ノ浦(現在、関門橋が架かっている当たり)で平家軍と源氏軍が激突することになった。

壇ノ浦の合戦は、海戦である。双方が船に乗って矢の打ち合いや船に飛び乗っての斬り合いをする。大将や身分の高い人たちは、唐船と呼ばれる高級な船に乗っていて、侍達はいわゆる兵船に乗るのが普通だったようだ。ところが、このとき平家方には唐船と兵船を入れ替える作戦があった。身分の高い人達を兵船に乗せ、唐船の方に侍を乗せる。すると源氏方は唐船の方を攻めてくるだろうから、そこを挟み撃ちにしようというものだった。
ところが、この計略は失敗に終わった。というのは先に書いた、田口重能が、平家方として参戦しながら、合戦の最中に寝返って源氏につき、身分の高い人達が乗っている兵船を攻撃したので、源氏方に計略がバレてしまい、平家方は劣勢に陥った。
壇ノ浦の合戦では、勇ましい話はあまり無いようで、どちらかというと平家一族の悲壮な死に方の描写が目立つ。とくに悲壮極まるのが、わずか8歳の幼帝、安徳天皇の入水である。時子(清盛の未亡人)が「我が身は女であっても敵の手にかかって死ぬつもりはない。帝のお供に参る。志のある者はあとに続きなさい」と女房たちに呼びかけ、「波の下にも都がございます」と帝を慰めて、曲玉と草薙剣を携えて帝とともに入水した。(注3)
たくさんの人が入水し、ほとんどの人が死んだ。しかし建礼門院と総大将の宗盛を含む80人ほど(注5)が源氏方に助けられ捕虜になったという。三種の神器のうち八咫鏡と曲玉は入れ物が海面に浮いて見つかったが、草薙の剣は海底に沈んでしまった。源氏方が近くの海女を動員して必死で捜索したが見つからなかったという。(注4)この合戦をもって、平家はほぼ全滅し、源氏方の勝ちとなった。このあと戦後処理につづく。
YouTubeのまんが日本昔話の公式サイトに「耳なし芳一」の話がアップされているので紹介する。壇ノ浦の合戦で死んだ平家の人々の亡霊が、芳一の琵琶の弾き語りを聞きに来る話。
下記URL。
https://youtu.be/vGxf8jgB7ds
***
(注1)熊野権現。この時代、熊野詣(もうで)が非常に流行した。清盛も重盛も詣でたし、維盛も屋島を抜け出して高野山に滝口入道を訪ねたときに熊野にも詣でている。また鹿ヶ谷の陰謀で鬼界が島に流された3人のうち俊寛を除いた2人も島に熊野権現を勧進して帰郷を祈願している。別当というのは宮司のリーダー。湛増(たんぞう)とは(わかりにくいが)人名である。
(注2)壇ノ浦の前に、京の都で後白河院と摂関家がそのような話し合いをしていたらしい。
(注3)安徳天皇は歴代の天皇の中で、戦乱が原因で亡くなった唯一の天皇である。
(注4)現在の草薙の剣は、伊勢神宮から献上されたものだいう。(Wiki情報)
(注5)平家物語の記述によると、武将38人、女房43人とある。

壇ノ浦の合戦の前、平家を取り巻く環境がどうなっていたのかをちょっと整理してみた。というのは、屋島が終わったあと、近くの有力者たちの寝返りが結構起きていて、壇ノ浦のとき、実際はもう放っておいても負けるような状態になっていたのだ。
まず九州。義仲に京を攻められて都落ちをしたときに、平家一族は一旦太宰府に入ろうとしたが、地元の侍がすべて源氏方についていて追い出されてしまい、居場所がなくなった結果、屋島に落ち着いたという経緯があった。
つぎに熊野権現の別当、湛増(注1)。この人はもともと平清盛と良好な関係にあったが、戦況が源氏に有利になり、リーダーとして源氏につくか、平家につくかの判断を迫られた。平家物語には書かれていないが、源氏と平家、双方から味方につくように迫られていたようで、中立という選択肢はなかったようだ。湛増は戦の行方を闘鶏で占い、源氏につくことにしたという。平家にとっては神に見放されたも同じである。
それから、四国の有力武将たち。伊予の武将、河野通信(こうのみちのぶ)、この人はもともと源氏方だった。彦島に対して四国のこの位置に味方がいるというのは源氏方にとってはかなり有利だったのではないか。
また四国の最大勢力の田口家は平家方であったが、屋島のあと、義経の部下の説得工作により田口教能(たぐちのりよし)が投降。総勢3000騎が源氏方につくことになった。そして極めつけが、田口重能(たぐちしげよし)。この人は田口教能の父親で、壇ノ浦の合戦の直前、息子が源氏方についたことを知り、合戦の最中に寝返り、勝敗を決定つけることになる。
・・・という四面楚歌の状態である。こういう場合、現代人ならば、おそらくほとんどの人が「もう無駄な殺生はやめ、平和的な説得工作に徹した方がいいのではないか」と考えるだろうし、実際そういう考えもあったらしい(注2)が、当時の武士の使命感が「敵と戦って首を取り、勝って報償をもらうこと」なので、何もせずに静観するということは、結局できなかったのではないか。これは僕の想像である。
さて源氏が瀬戸内海側、つまり東側から彦島に攻め込もうとすれば、関門海峡を通る必要がある。屋島が終わって1ヶ月後の3月。壇ノ浦(現在、関門橋が架かっている当たり)で平家軍と源氏軍が激突することになった。

壇ノ浦の合戦は、海戦である。双方が船に乗って矢の打ち合いや船に飛び乗っての斬り合いをする。大将や身分の高い人たちは、唐船と呼ばれる高級な船に乗っていて、侍達はいわゆる兵船に乗るのが普通だったようだ。ところが、このとき平家方には唐船と兵船を入れ替える作戦があった。身分の高い人達を兵船に乗せ、唐船の方に侍を乗せる。すると源氏方は唐船の方を攻めてくるだろうから、そこを挟み撃ちにしようというものだった。
ところが、この計略は失敗に終わった。というのは先に書いた、田口重能が、平家方として参戦しながら、合戦の最中に寝返って源氏につき、身分の高い人達が乗っている兵船を攻撃したので、源氏方に計略がバレてしまい、平家方は劣勢に陥った。
壇ノ浦の合戦では、勇ましい話はあまり無いようで、どちらかというと平家一族の悲壮な死に方の描写が目立つ。とくに悲壮極まるのが、わずか8歳の幼帝、安徳天皇の入水である。時子(清盛の未亡人)が「我が身は女であっても敵の手にかかって死ぬつもりはない。帝のお供に参る。志のある者はあとに続きなさい」と女房たちに呼びかけ、「波の下にも都がございます」と帝を慰めて、曲玉と草薙剣を携えて帝とともに入水した。(注3)
たくさんの人が入水し、ほとんどの人が死んだ。しかし建礼門院と総大将の宗盛を含む80人ほど(注5)が源氏方に助けられ捕虜になったという。三種の神器のうち八咫鏡と曲玉は入れ物が海面に浮いて見つかったが、草薙の剣は海底に沈んでしまった。源氏方が近くの海女を動員して必死で捜索したが見つからなかったという。(注4)この合戦をもって、平家はほぼ全滅し、源氏方の勝ちとなった。このあと戦後処理につづく。
YouTubeのまんが日本昔話の公式サイトに「耳なし芳一」の話がアップされているので紹介する。壇ノ浦の合戦で死んだ平家の人々の亡霊が、芳一の琵琶の弾き語りを聞きに来る話。
下記URL。
https://youtu.be/vGxf8jgB7ds
***
(注1)熊野権現。この時代、熊野詣(もうで)が非常に流行した。清盛も重盛も詣でたし、維盛も屋島を抜け出して高野山に滝口入道を訪ねたときに熊野にも詣でている。また鹿ヶ谷の陰謀で鬼界が島に流された3人のうち俊寛を除いた2人も島に熊野権現を勧進して帰郷を祈願している。別当というのは宮司のリーダー。湛増(たんぞう)とは(わかりにくいが)人名である。
(注2)壇ノ浦の前に、京の都で後白河院と摂関家がそのような話し合いをしていたらしい。
(注3)安徳天皇は歴代の天皇の中で、戦乱が原因で亡くなった唯一の天皇である。
(注4)現在の草薙の剣は、伊勢神宮から献上されたものだいう。(Wiki情報)
(注5)平家物語の記述によると、武将38人、女房43人とある。
前の10件 | -